高齢ドライバー問題は「西高東低」!意見・要望への反応から見えるこの問題の実態
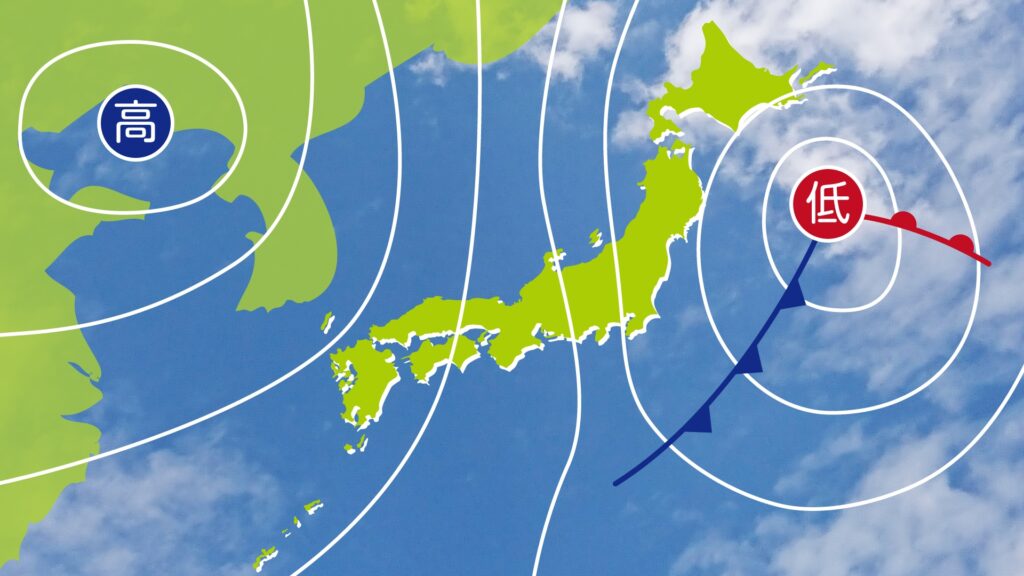
社会問題への提言と活動の広がり
全国的に高齢ドライバーによる加害事故が連日のように発生し、社会問題として大きく取り上げられています。私たちはこの問題の解決に少しでもお役に立ちたい、という想いから活動を続けています。その一環として、私たちが考える具体的な問題解決に向けた提言を動画にまとめ、関係者の皆様にご覧いただけるよう公開しました。
作成した動画は、都道府県警の皆さん向け、地方自治体の皆さん向け、そして民間企業の皆さん向けの3種類です。内容が同じであればわざわざ複数作成する必要はありませんが、それぞれの立場で高齢ドライバーの事故防止対策を実施する際の着眼点や影響が異なるため、あえて3種類作成し、異なる切り口で説明を行いました。
反響から見えた「西高東低」の傾向
これらの動画は、各県警や地方自治体、民間企業の皆さんの公式ウェブサイトや郵送などを通じて広く情報提供させていただきました。その結果、ありがたいことに多くの方々にご視聴いただき、中にはお問い合わせやアドバイス等を頂戴しております。お忙しい中、私たちの意見に耳を傾け、関係組織内でご議論等いただいたことに改めて感謝申し上げます。
一方で、私たちの文才のなさと文字数制限などが原因で説明が不十分になり「高齢ドライバー問題への意見・要望=警察案件」と誤解させてしまい、その都度、こちらからの追加説明させていただく時間が生じてしまったことは、大変申し訳なかったと感じています。これは今後の課題として改善に努めてまいります。いずれにしても、何らかの反応をいただけたことは、私たちにとって非常にうれしいことでした。
ところで、この問題の受け止め方に組織・エリアごとになんらかの温度差があるのだろうか、という思いから皆さまの反応を注視することにしました。具体的にはどこから、どのような反応や関心が寄せられているのかを分析することで、この問題の特性や市場の有無が見えてくるのではないか。その結果、軽々な判断はまだできないものの、私たちが感じたのはこの問題への意識が「西高東低」という傾向でした(ここでいう東西の分け方は、一般的な世間の概念とは多少異なるかもしれません。私がNTT出身なので、NTT東西のエリア区分に準じて東西を分けて考えています)。
つまり、西日本からの問い合わせや反応が多く、東日本はそれに比べてやや少ない、という傾向が見えてきました。もちろん、都道府県の数だと東日本が17都道県、西日本が30府県になるので、約2倍の差があることも一因としてあると思います。しかし、このデータは、私たちがまだ認識できていない事実を如実に表しているのかもしれません。この傾向を受けて、私たちは「高齢ドライバー問題が深刻なのは、東日本よりも西日本ではないか」という仮説を立て、その検証を試みました。
高齢ドライバー問題が「西高東低」という仮説の検証
私たちはこの「西高東低」という仮説の背景には、具体的な社会・経済的要因があるのではないかと考え、調査・考察を進めました。その結果分かってきた3つの事実を解説します。
1. 高齢化の「質」が異なる東西の高齢化率
高齢ドライバー問題の深刻度は、その地域の高齢化の進み具合と密接に関わってきます。私たちが定義する東西の区分で高齢化率(2023年時点)を見ると、東西の平均値に大きな差はありませんでした。
- 東日本の平均高齢化率:約31.6%
- 西日本の平均高齢化率:約31.7%
しかし、この数値の裏側には、高齢化の「質」という点で看過できない違いがあります。東日本には、東京都(高齢化率22.8%)や神奈川県(25.9%)といった、全国でも高齢化率が極めて低い大都市圏が含まれており、これらの地域が東日本全体の平均値を大きく引き下げています。
一方で、西日本には、高知県(36.3%)、徳島県(35.3%)、島根県(35.0%)のように、高齢化率が非常に高い地方圏が数多く含まれています。これは、西日本に高齢化がより深刻な地域が多く存在し、高齢ドライバーの割合が相対的に高い環境にあることを示唆しています。
2. 日常生活における「車社会」への高い依存度
高齢ドライバー問題の背景には、高齢者の生活における車の位置づけが深く関係しています。特に西日本は、東日本に比べて地域全体の車への依存度が高い傾向が見られます。この事実は、ちょっとデータが古いですが総務省統計局の国勢調査データ(2010年)における通勤・通学手段の比較から明確に読み取ることができます。
- 西日本の平均的な自家用車のみ通勤・通学率:約55%
- 東日本の平均的な自家用車のみ通勤・通学率:約45%
ここから、西日本の方が、東日本と比較して通勤・通学において自家用車に依存している人の割合が高いことがわかります。東日本には、鉄道やバスなどの公共交通機関が非常に発達した大都市圏(例:東京都の自家用車通勤・通学率は約11%、神奈川県は約22%)が含まれるため、これらが東日本全体の自家用車依存率を大きく引き下げています。
対照的に、西日本の多くの地方圏では、公共交通機関の選択肢が乏しく、日常生活の移動手段として自家用車が「必須」となっている地域が多く存在します。これは郊外に開発されたニュータウンが多く存在し、そこで生活している住民が車なしでは生活が成り立たない構造が定着しているからと考えられます。このような状況は、高齢者に限らず、地域全体として車に頼らざるを得ない実態を示しており、高齢ドライバーにとっては「免許返納=移動手段の喪失」という深刻な問題に直結する可能性が高いと言えます。
3. 高齢ドライバーによる「加害事故」が多い傾向
前述の高齢化の「質」と高い自動車依存度が複合的に作用することで、西日本では高齢ドライバーが「加害者」となる事故のリスクが相対的に高い傾向にあることが示唆されます。残念ながら、東西で「高齢ドライバー(第一当事者)による事故件数」を直接集計・比較できる公式データは公表されていません。しかし、「人口10万人当たりの交通事故死者数」のデータから、その傾向を間接的に読み取ることが可能です。
2023年の「人口10万人当たり交通事故死者数」の都道府県別ランキングを見ると、上位10県のうち、9県が「西日本」の地域に集中していることがわかります。
| 順位 | 都道府県 | 人口10万人当たり交通事故死者数 (人) | 東西区分 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 徳島県 | 4.75 | 西日本 |
| 2位 | 愛媛県 | 4.03 | 西日本 |
| 3位 | 山口県 | 3.93 | 西日本 |
| 4位 | 高知県 | 3.49 | 西日本 |
| 5位 | 香川県 | 3.39 | 西日本 |
| 6位 | 和歌山県 | 3.32 | 西日本 |
| 7位 | 島根県 | 3.25 | 西日本 |
| 8位 | 秋田県 | 3.24 | 東日本 |
| 9位 | 宮崎県 | 3.19 | 西日本 |
| 10位 | 滋賀県 | 3.16 | 西日本 |
このランキングは、高齢者による事故だけではありませんが、高齢化が進み、かつ車への依存度が高い西日本に交通死亡事故全体のリスクが高い地域が集中していることを強く示唆しています。
対照的に、東日本の中でも人口が多い大都市圏(東京都:1.04人、神奈川県:1.78人、埼玉県:1.67人、千葉県:2.03人)では、公共交通機関が発達しており、高齢ドライバーが車に乗る機会が相対的に少ないため、「人口10万人当たり交通事故死者数」が低い傾向にあります。このことが、東日本全体の数値に影響を与えていると考えられます。
これからの高齢ドライバー問題解決に向けて
以上の分析から、私たちが立てた「高齢ドライバー問題への関心は西日本の方が高い」という仮説は、ある程度検証できたように感じています。もちろん、これは専門家による綿密な調査ではなく、私たちのデータ分析に基づく「お遊び」の範疇を出ないものかもしれません。
しかし、重要なのは、どこに「市場」があり、どこでこの問題に困っている人が多いのか、という視点です。困っているエリアから問題解決に着手するというのが、原則だと考えます。つまり、高齢ドライバーによる事故対策を講じる際に、地域ごとの特性、特に高齢化と車社会化が進んだ地域の事情を深く理解し、画一的ではない、より実効性のある対策を推進する必要性を強く示唆しているのではないでしょうか。
私たちは、この「高齢ドライバー問題は西高東低」という傾向を真摯に受け止め、私たちが提供できる情報や支援を通じて、この喫緊の社会問題の解決に微力ながら貢献できるよう、これからも活動を続けていきたいと考えています。
