野村克也著「野村再生工場」から学ぶ~高齢ドライバーと家族に贈る免許返納問題解決への道~
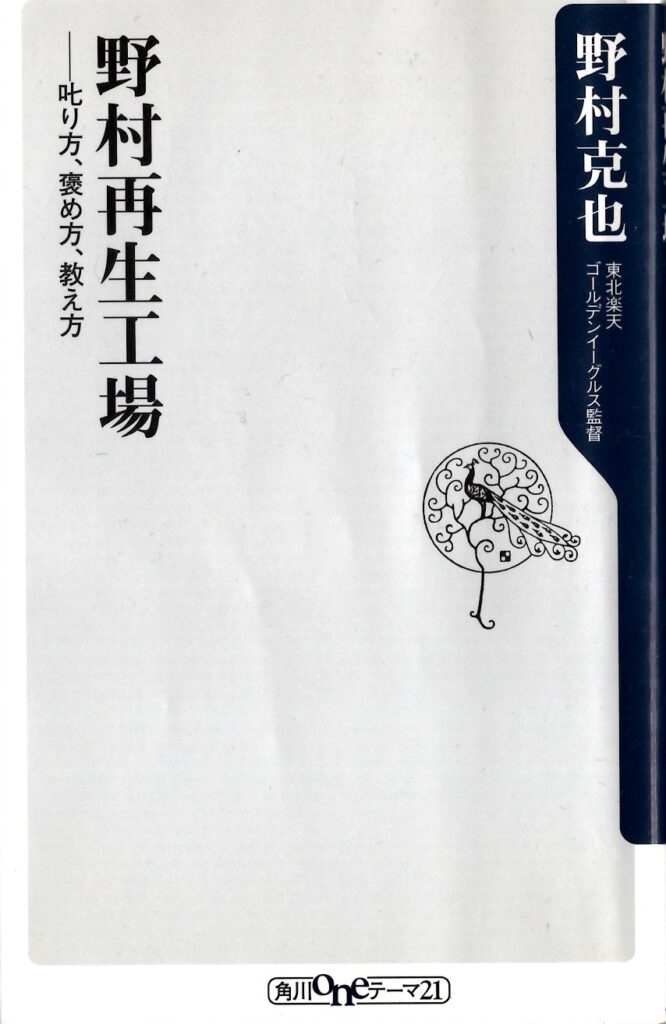
私が育ったのは、千葉県佐倉市です。野球ファンの方なら、「長嶋茂雄氏の出身地」としてピンとくるでしょう。同じ小学校の大先輩である長嶋茂雄氏の活躍ぶりには、後輩として尊敬の念を抱き、その多方面に渡る活躍に注目していました。
その長嶋茂雄氏と「ひまわりと月見草」という例えで比較されるのが、野村克也氏(先日訪れた京丹後市出身)です。長嶋茂雄氏が「カンピュータ」の野球なら、野村克也氏はデータと緻密な分析に基づく「ID野球」。常にこの二人は対比されてきました。私は、ミスター・ベースボール長嶋茂雄氏の活躍に目を凝らす一方で、野村克也氏の動きにも目が離せませんでした。特に、当時テレビ等で報じられる監督時代のコメントには関心をもって耳を傾けていたものです。
そんな野村克也氏の著書が私の本棚にあり、久しぶりに読み返してみると、自動車の安全運転、特に高齢ドライバーの問題に通じる示唆に富んだ記述が多く、ハッとさせられました。今回は、この著書から得られた教訓を、高齢ドライバーの事故が多い問題を家族や友人とともに考えるためのヒントとして読み替え、振り返ってみたいと思います。
問題解決のために「考える運転」への転換
本章では、野村克也氏の著書『野村再生工場』(角川oneテーマ21)の中から、高齢ドライバーの事故が多い、という問題の解消を図る上で、特に重要だと感じたフレーズを抜き出し、その教訓を高齢ドライバーとその家族や友人に当てはめて、具体的に考えてみます。
1. 家族の厳しさの裏にある愛情
「(人は)期待するから叱る。」
親や友人である高齢ドライバーの運転に危険を感じた家族等が、免許返納を強く勧めるのは、事故を起こさず、平穏で充実した生活を送って欲しいという「期待」と「愛情」の表れです。
高齢ドライバーのどこに問題があり、それを直すためにどのような「対処方法」があるのかを自ら考え、その実行に向けて努力することで、高齢ドライバーとして家族や友人の期待にどのように応えるべきかを探る必要があります。
2. 原因分析と対処が鍵
「「失敗」と書いて「せいちょう」と読む」
車に小さな傷をつけた程度の「失敗」を家族が感情的に本人を責めてしまえば、ドライバーとしての成長などありえません。しかし、何も考えず、慣れた技術だけで失敗を表面だけカバーしようとすれば、同じ過ちを必ず繰り返します。
重要なのは、失敗の原因をしっかり分析し、それに対する具体的な対処方法を考えることです。これは、単なる技術論ではなく、運転に対する「考え方」を変えるための大きな一歩となります。
3. 家族が提供すべき「気づきの機会」
「人間は失敗してこそ自分の間違いに気づくものだ」
高齢ドライバーは、他者から指摘されても、自分の運転能力の低下を真剣に受け止めないことが多いです。実際に車に小さな傷をつけるなどの「失敗」を経験して、はじめて自分の考え方が間違っているのではないか、と思うようになります。
他人に迷惑をかけるような大きな事故では困りますが、そうではない小さな失敗は、ある意味「必要悪」と捉えるべきです。家族や友人はその失敗を逆手に取り、ただ免許返納だと大騒ぎするのではなく、今後についてお互いに冷静に考える絶好の機会と捉えて、徹底的に議論するべきです。
このとき、家族や友人は高齢ドライバーに問題意識が高まるような「アドバイス」をし、本人に疑問が生まれるように仕向けることが重要です。「どうしたらいいか?」と高齢ドライバー側から聞いてきたときこそ、家族や友人の出番です。突き放すのではなく、具体的な対策(例:いつまでに、どのような技術を習得するか、等)について、一緒に考えることが重要です。
4. 「シンキング・ドライビング」の植え付け
「自ら取り組もうとする意欲を促すことが必要」
運転能力の低下を受け入れ、運転を継続するなら何らかの対処が必要だと高齢ドライバーが考えるようになったとしても、技術を教えるのは最後で構いません。その前に、自ら能動的に取り組もうとする「意識」を植え付けることが大切です。
その際、「今後も運転を継続して、どこか行きたいところがあるか」「運転を続けることで、どのような充実した生活を送りたいか」という今後の目標を明確に聞き出すことがポイントとなります。そして、「目標を達成するために足りないものは何か」「何をしなければならないか」を考え、これらの課題に対して自ら真摯に向き合う必要があります。これが「シンキング・ドライビング」です。
頭を使い、現状の自分の運転で何が不足し、何をどれだけ補う必要があるかを明らかにすることで、たとえ体のあちこちが衰えはじめても、十分に安全な運転は継続できます。具体的には、認知能力の変化に対応した運転する時間や運転する範囲を限定するなどが考えられます。
5. 「考え方を変える」ことが信用回復の鍵
「人生とは生きることが目的」
高齢ドライバーが人生を「いかに生きるか」を考えるようになれば、当然、運転に関する取り組みも変わってきます。しかし、無事故の実績がある高齢ドライバーほど、「このままでいい」「変わる必要性を感じていない」と信じていることが多いのも事実です。
しかし、人間の評価とは他人がどう感じるかによって決まります。一度落ちた評価を覆すためには「うちの親、変わったな」と周囲に感じさせる必要があります。失敗等により失った信用を取り戻すためには、言葉ではなく、日常の行動と、運転に対する「考え方を変える」努力を示すしかありません。この「行動と考え方を変えられるか」が、運転を継続したい場合できるかどうかが非常に大きな分かれ目となります。
6. 家族の「観察」と「責任」
「考え方を変えるためには、本人が気づくことができるかにかかっている」
家族や友人の役割は、高齢ドライバーにいかに問題に気付かせることができるかにかかっています。運転能力が衰えても、これまでのやり方と同じ方法で運転を続けようとしている、という点に気付かせることが、家族や友人の使命です。
そのために、家族や友人は高齢ドライバーを「観察する」ことが重要です。もし、運転を継続するための能力が残っているのに、家族や友人の怠慢や無理解によって運転免許を返納させられた高齢ドライバーは、家族や友人の怠慢の犠牲者と言えるかもしれません。家族や友人は、その判断ひとつで、高齢ドライバーの残りの人生が大きく変わってしまう、とてつもない大きな責任を負っていることを認識しなければなりません。
家族や友人は、高齢ドライバーの隠れた才能や長所を発見し、引き出し、それを活かす方法を教える必要があります。
納得感のある結果を導く、という選択肢
これらの情報は、野村克也氏が、かつて活躍した野球選手が再びスポットライトを浴びるように、「野村再生工場」と言われるやり方で結果を残すために何を考え、どう行動したか、という情報をもとにしたものです。
かつて、家族や友人を車に乗せ、いろいろなところに連れて行ってくれた高齢ドライバーは、子どもたちなどの目からは、プロ野球の選手のように光輝いていたことでしょう。しかし、歳が経つにつれてその光が輝きを失ってきているかもしれません。そんなときに、正しい判断をして、正しい道に導くのは、野村克也氏が果たした役割を家族や友人ができるかが、重要となります。
高齢ドライバーの状態を観察して、危険だと感じれば、免許返納(野球で言うと引退)という選択もせざるを得ません。しかし、野村克也氏がやったように、「まだ運転できる」という高齢ドライバーには、必要な対応を取ることで「再生」も可能であり、それで輝きを取り戻し、現役続行を果たすこともできるはずです。誤った判断が取り返しのつかないことになりかねないのは、野球の世界も、高齢ドライバーの世界も同じです。
だからこそ、家族が一方的に免許返納、と決め付けてしまうのではなく、本当に免許返納すべきなのか、安全に運転を継続させるための対策を打てば問題を解消・軽減できるのではないか、ということを考え、最終的に高齢ドライバー自らが納得感のある「引退」または「現役続行」を決めさせる、という選択肢も考えるべきではないでしょうか。
高齢ドライバーの気持ちも考慮しながら、高齢ドライバーの状態を冷静に観察・判断する家族や友人の関わりこそが、高齢ドライバーが最後まで充実した人生を送るための鍵となります。
参考文献
- 『野村再生工場』 野村克也著 (角川oneテーマ21)
