これってわがまま?健康寿命を延ばすために運転を続けることの是非 ”一挙両得”の行動がマル◎
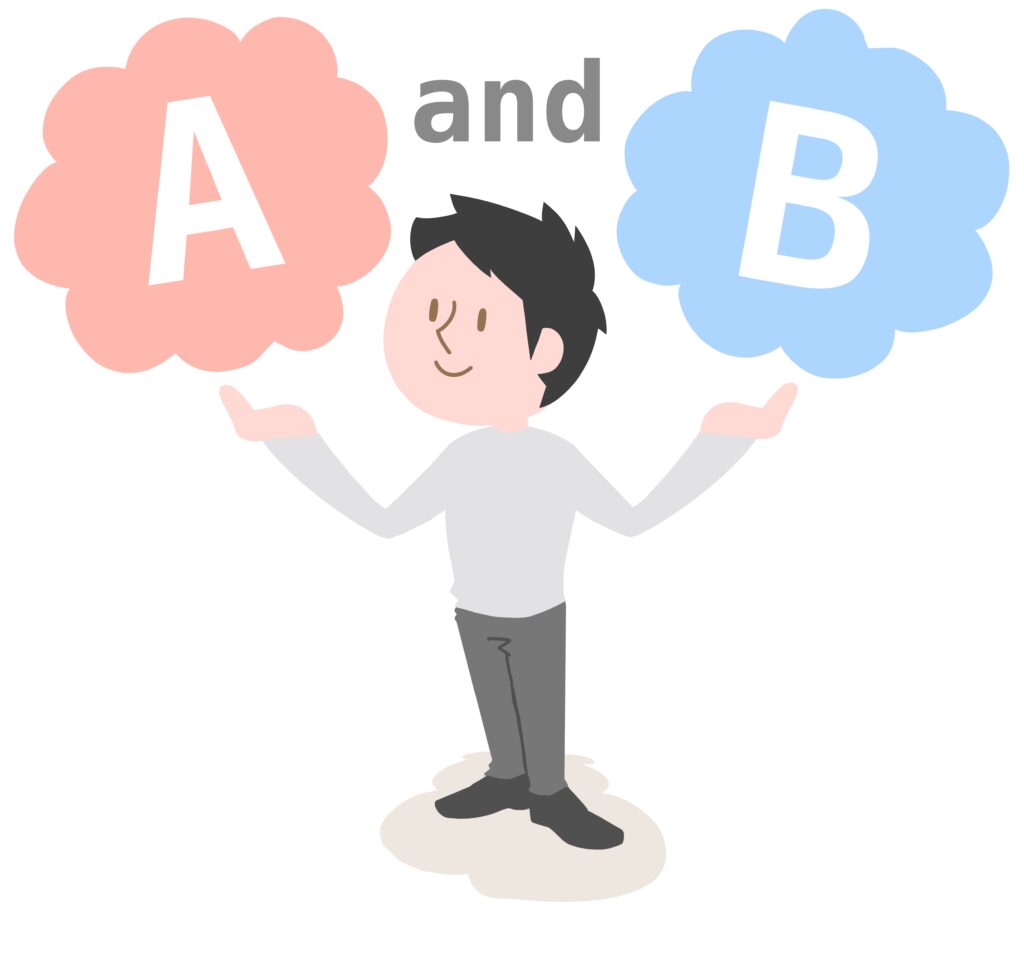
矛盾するようで矛盾しない発想
「認知症予防のために車を運転する」という考え方には、一見すると矛盾があり、かつ受け入れがたい内容が含まれているように思えます。なぜなら、事故を起こす可能性がある運転という行為を、自らの健康のために実行するのは、身勝手ではないかという批判があるからです。
だからと言って、高齢ドライバーは「免許を返納すべきか」、それとも「運転を続けるべきか」という二択では問題解決しません。そこで役立つのが、「パラコンシステント(矛盾許容論理)」という考え方です。
健康寿命と認知症予防
日本人の健康寿命は平均74.1歳、それに対して平均寿命は84.3歳と言われています。つまり、この差の約10年間は「健康ではない期間」が続くことになります。この間は「不健康寿命」や「要介護期間」と呼ばれ、介護や病気による制約を受ける可能性が高くなります。
多くの人は、できるだけ健康寿命を延ばし、不健康寿命を短くしたいと考えます。そのためには、脳を鍛える運動や食生活の改善、ストレスケアが重要とされています。そして、衝撃的な事実として、「車の運転をやめると要介護になる割合が8倍」というデータもあるのです。
これは、運転が脳を活性化させ、認知症予防に一定の効果を持つ可能性を示唆しています。しかし、「認知症予防のために運転を続ける」という考えが、事故のリスクを増やすことに対する社会的な批判を受けるのも事実です。
「パラコンシステント」という視点
「事故を防ぎながら運転を続ける」という発想は、一見矛盾するように見えます。しかし、最近読んだ『NTTの叛乱』(堀越功著)の中で紹介されていた「パラコンシステント」という考え方が、解決のヒントになるかもしれません。
パラコンシステント論理とは、矛盾を許容しつつ論理体系を維持する考え方です。通常の論理では、矛盾があるとすべてが破綻してしまいます。しかし、パラコンシステント論理では、「矛盾があっても、それを制御して活用できる」と考えます。現在の世界情勢においては、どの企業もサスティナビリティ(持続可能性)と企業成長、グローバリズムと保護主義など、矛盾や対立する概念を両立することが求められています。
これを運転に当てはめると、「認知症予防のために運転を続ける」ことと「事故を防ぐ」ことは両立可能だという発想になります。
積極的な行動で矛盾を解決する
この両立を可能にするためには、これまで実施してこなかったかもしれないような、新たな対策を積極的に行うことが重要です。
ドライバーも高齢者になると運転能力の低下が起こりますが、その原因の多くは身体機能の衰えにあります。しかし、適切な訓練と対策を行えば、事故リスクを大幅に抑えることができるのです。
具体的には、以下のような対策が考えられます。
- 運転に必要な身体機能を維持・向上させる
- 目の検査・聴力チェックを定期的に実施
- 反応速度を鍛えるトレーニング、適度な運動を習慣化
- 認知機能のチェックを定期的に行い、自覚を持つ
- 運転環境を工夫する
- 運転ルートを事前に計画し、難しい道を避ける
- 日中の明るい時間帯や晴天時に運転する
- 安全機能付きの車を活用する(自動ブレーキ、誤発進防止機能など)
- 家族や第三者との協力を強化する
- 家族と運転について定期的に話し合う
- 専門家等の第三者のアドバイスを受け入れる
建設的な選択を
「運転をやめることが一番の事故防止」という意見もあります。しかし、その考え方だけでは、「健康寿命を延ばしたい」という高齢者の願いとは噛み合いません。
だからこそ、運転継続と事故防止を両立させる「積極的な活動」が重要です。安全運転のために努力することは、結果的に健康寿命の延長にもつながり、家族の安心にもなるのです。
デジタル化が進む世の中においても、こうしたアナログ的な発想が時に求められます。「ゼロかイチか」ではなく、その「中間的な解決策」を考え、行動すること。それが、「パラコンシステント」な発想を活かした新しい高齢ドライバーのあり方なのではないでしょうか。
