アクセルとブレーキの踏み間違い 足からのSOSを見逃さず、適切な対処により主導権を握ろう
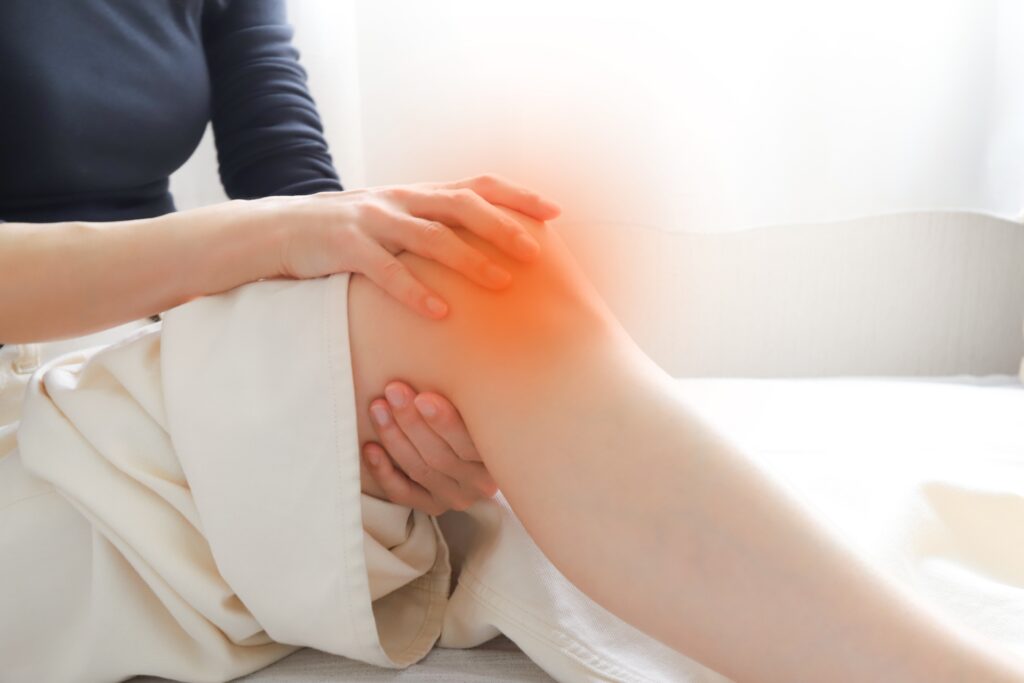
忘れたころにやってくるのは、災害だけではない
「災害は忘れたころにやってくる」。昔よく耳にしたこの言葉は、私たちに常に「備える」ことの重要性を伝えるための教訓です。しかし、この「忘れたころにやってくる」のは、自然災害だけではありません。高齢ドライバーによる痛ましい事故。このニュースを見るたびに、私はいつもこの言葉を思い出します。
誰もが「自分は大丈夫」「まだまだ運転できる」と考えているかもしれませんが、私たちは必ず加齢という名の「自然の摂理」に直面します。若い頃は難なくできていたアクセルとブレーキの踏み分けも、いつの間にか運転能力が衰えていることに気づかずに足の筋力や関節の柔軟性が失われ、思ったように操作できなくなることがあるかもしれません。そしてほんの少しの判断の遅れや、ほんの一瞬の足の動きが鈍ったことで、取り返しのつかない事故につながってしまう。それはまさに、私たちの危機感が薄れた「忘れたころ」に、突然降りかかってくる災害のようなものだと思います。
事故を起こした高齢ドライバーの多くが口にする理由としては「アクセルとブレーキを踏み間違えた」というものです。現役世代の私たちからすると、「どうしてそんな間違いが起きるんだろう?」と疑問に思うかもしれません。しかし、以前「老いパーク」を訪れた際、高齢になるというのは「重いおもりを付けて歩いているようなもの」だとわかりました。それを知ったとき、もしも運転するときにそんなおもりが足についていたら、思うように足を動かすことができず、確かに事故も起こるかもしれない、という印象を受けました。こうしたものは、実際に体験してみなければ、なかなか理解できないものなのかもしれません。
「足寿命」を知り、衰えに抗う
高齢になると足の機能が衰え、それが原因でアクセルとブレーキを踏み間違えてしまう。もし本当にそんなことが起きるのなら、足の衰えに抗うための対策を講じるのが一番手っ取り早いのではないか。そう考えるのは、ある意味で「言葉遊び」のようにも聞こえますが、この発想は決して間違っていないと思います。
そこで、足の機能と対策について知るために、菊池守氏の著書『100歳までスタスタ歩ける足の作り方』を読んでみました。 そこで分かったのは、まず「足は消耗品」だということです。歩くときは体重の2~3倍、走るときは約5倍もの負担がかかっているように、足は体の中で最も酷使されている部位であるという事実を改めて知りました。その結果、加齢とともに足のトラブルが重なると、やがて「歩けなくなる」、つまり「足寿命が尽きる」ことになってしまうとのことです。 にもかかわらず、私たち多くの人は足に寿命があることすら知らずに過ごしていると思います。足のトラブルは他の疾患に比べて軽視されがちですが、これらは実は足の寿命が短くなっているサインなのかもしれません。
足の老化の代表的な要因は、加齢による筋力の衰えと関節の硬化とのことです。これによって、足裏の土踏まず部分にある「アーチ」と呼ばれるカーブが崩れ、偏平足が進行します。そして足のバランスが崩れると無理な負担がかかり、歩行困難へとつながっていくのです。足の衰えは知らないうちに進行しているため、足が発するSOSをいち早く見極め、適切なケアをしないと、足の機能はどんどん失われていく、とのことです。
運転を続けるために、足を若返らせる
足に起きるトラブルの原因が分かったところで、その対策はあるのでしょうか。 車を安全に運転し続けるためには、足の機能を麻痺させないことが何よりも大切、とのことです。そして、足は努力次第でいくつになっても元気を取り戻すことができる、とも本では述べられています。
足の寿命を延ばすために重要なのは、「足首の柔軟性」「土踏まずの形」「足裏の筋力」の3つ、とのこと。これらの機能を鍛えれば、足の機能はどんどん回復し、足寿命を若返らせることが可能とも。 具体的な対策として効果的なのが、定期的な運動。特に、足首が硬くなるのを防ぐためには、関節の柔軟性と筋力の両方を維持する必要があります。ジョギングのような運動も大切ですが、筋肉を鍛えることはできても、硬くなったアキレス腱を柔らかくすることはできません。そこで、アキレス腱を含めた足の機能全体に作用する「スタスタ体操」というものがあり、足に特化した運動を取り入れるのが効果的と紹介されています。
また、「歩く」ことも非常に重要とのこと。 1日2,000歩で筋肉の衰えを防ぎ、4,000歩で脳に刺激を与え、7,000歩で血管や骨を鍛え、そして8,000歩まで達すると、高血圧や糖尿病、脂質異常症の予防にも効果があると紹介されています。 歩くことは単なる全身運動ではなく、認知機能の維持にもつながります。日頃からよく歩く人ほど認知症を発症しにくいというデータもあるように、脳の血流を維持することは、神経細胞の再生が難しい高齢者にとって非常に大切なのだそうです。
自分で行動し、時の流れを自分でつくる
「足は第二の心臓」という言葉があり、老化は足から始まると言われています。 車の運転は、視覚や聴覚、ハンドルを操作する手、そしてアクセルやブレーキを操る足と、頭からつま先まで全身を使う行為です。もしそのうちの足を中心とする下半身部分が思ったように動かせない状態であれば、いくら頭の機能が優れていても、制動を司る足が制御できないことで、建物や他の車に突っ込んでしまう、といった事故が起きるのは説明がつきます。
しかし、先ほどお伝えしたように、体は年齢とともに衰え始めたら何も対処できない、というわけではありません。自然の摂理にただ従う必要はなく、足の状態は自分でコントロールできるのです。 つまり、地震の発生を抑制することはできませんが、足の健康は自分で管理・操作することができます。 だったら、時の流れに身を任せるのではなく、自分の手で「流れ」をつくり、自ら行動する。そんな積極的な生き方の方が、ずっといいと思います。 自分でコントロールし、アクティブに生きることは、家族や周囲にも良い影響を及ぼし、一度きりの人生を後悔なく生きることにもつながるはずです。
高齢ドライバーの方が安全運転を続けるために、また、ご家族の方が大切な人の健康作りをサポートするためのいいきっかけ作りになれば幸いです。
